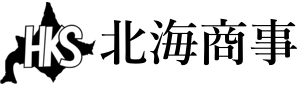遺品整理の費用はいくら?実際の見積もり事例と安くする5つのコツ

遺品整理の費用は間取りや物量によって大きく異なりますが、一般的な相場は1Kで3万円〜8万円、2LDKで8万円〜20万円程度です。
この記事では、実際の見積もり事例をもとに間取り別の料金相場を詳しく解説し、費用が高くなる要因と安くするための具体的な5つのコツをご紹介します。
事前整理や複数見積もりの取得など、適切な方法を実践することで、遺品整理費用を20〜30%程度削減することも可能です。信頼できる業者の選び方や見積書の確認ポイントも含めて、遺品整理の費用に関する疑問をすべて解決します。
遺品整理の費用相場と料金体系

遺品整理の費用は、依頼する内容や条件によって大きく変動します。
一般的な費用相場を知ることで、適正な料金で依頼できるかどうかを判断できます。ここでは、間取り別の費用相場や基本料金の内訳、追加料金が発生するケースについて詳しく説明します。
間取り別の遺品整理費用相場
遺品整理の費用は、部屋の間取りによって大きく異なります。以下が一般的な費用相場です。
1Kや1DKの場合、費用相場は3万円から8万円程度です。比較的コンパクトな空間のため、作業時間も2時間から4時間程度で完了することが多いです。
1LDKや2DKの場合、費用相場は5万円から15万円程度になります。リビングスペースがある分、整理する物量も増えるため、作業時間は4時間から6時間程度かかります。
2LDKや3DKの場合、費用相場は8万円から25万円程度です。部屋数が増えることで、仕分けや搬出作業に時間がかかり、作業人員も3名から4名必要になることがあります。
3LDK以上の場合、費用相場は15万円から50万円程度となります。一戸建て住宅の場合は、庭や物置、車庫なども含まれることがあり、さらに費用が高くなる傾向があります。
これらの費用相場は、あくまで目安です。実際の費用は、物量や処分品の種類、建物の立地条件などによって変動します。
基本料金に含まれる作業内容
遺品整理の基本料金には、通常以下のような作業が含まれています。
まず、遺品の仕分け作業があります。貴重品や形見分けの品、処分品などを丁寧に分類し、依頼者の意向に沿って整理します。写真や手紙などの思い出の品は、特に慎重に扱われます。
次に、不用品の搬出作業です。家具や家電、衣類などの不用品を建物から搬出し、トラックに積み込みます。エレベーターがない建物では、階段を使った搬出となるため、作業員の負担も考慮されます。
簡易的な清掃作業も基本料金に含まれることが多いです。遺品を搬出した後の部屋を、ほうきやモップで清掃し、次の入居者や売却に向けて準備します。
廃棄物の適正処理も重要な作業です。一般廃棄物や産業廃棄物として適切に分別し、各自治体の規定に従って処分します。リサイクル可能な品物は、適切にリサイクル処理されます。
最後に、作業完了報告があります。作業前後の写真を撮影し、どのような作業を行ったかを報告書にまとめて提出します。
追加料金が発生するケース
基本料金以外に追加料金が発生するケースがいくつかあります。事前に確認しておくことで、予想外の出費を避けることができます。
特殊清掃が必要な場合は、大幅な追加料金が発生します。孤独死や自殺などで発見が遅れた場合、専門的な清掃と消臭作業が必要となり、10万円から50万円程度の追加費用がかかることがあります。
エアコンの取り外しや、仏壇・神棚の供養処分も追加料金の対象です。エアコンは1台あたり5,000円から1万円、仏壇の供養処分は3万円から5万円程度が相場です。
ピアノや金庫などの重量物の搬出には、特殊な機材や人員が必要となるため、追加料金が発生します。ピアノの場合は2万円から5万円、金庫は重量により1万円から3万円程度の追加費用がかかります。
建物の立地条件によっても追加料金が発生することがあります。トラックが建物の近くに停められない場合や、エレベーターがなく4階以上からの搬出の場合は、作業効率が下がるため追加料金の対象となります。
夜間や早朝、土日祝日の作業を希望する場合も、通常料金の20%から50%程度の割増料金が発生することが一般的です。これらの追加料金については、見積もり時に必ず確認し、総額でいくらになるのかを把握しておくことが大切です。
遺品整理の費用を決める5つの要因

遺品整理の費用は、さまざまな要因によって大きく変動します。見積もりを依頼する前に、どのような要素が料金に影響するのかを理解しておくことで、適正な価格かどうかを判断できるようになります。
ここでは、遺品整理の費用を左右する主な5つの要因について詳しく解説します。
部屋の広さと物量
遺品整理の費用を決める最も大きな要因は、部屋の広さと遺品の物量です。一般的に、1Kや1DKなどの単身者向けの部屋であれば3万円から8万円程度、2LDKや3LDKなどのファミリー向けの間取りでは10万円から30万円程度が相場となります。
ただし、同じ間取りでも物量によって費用は大きく変わります。例えば、ミニマリストの方の1Kと、長年住み続けて物が蓄積された1Kでは、作業量が2倍以上違うことも珍しくありません。特に、押入れや納戸、天井裏などに収納された荷物が多い場合は、見た目以上に作業時間がかかるため、費用が高くなる傾向があります。
処分品の種類と量
処分する品物の種類によって、処理費用が大きく異なります。
一般的な家庭ごみとして処分できるものは比較的安価ですが、家電リサイクル法の対象となるエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などは、リサイクル料金と収集運搬料金が必要になります。
また、仏壇や神棚などの供養が必要な品物、ピアノやエレクトーンなどの大型楽器、金庫などの重量物は、特別な処理や専門業者への委託が必要となるため、追加費用が発生します。一方で、貴金属やブランド品、骨董品など買取可能な品物が多い場合は、その分費用から差し引かれることもあります。
建物の条件と搬出環境
建物の構造や立地条件も、遺品整理の費用に大きく影響します。エレベーターのない集合住宅の上層階や、道幅が狭く作業車両が近くに停められない場所では、人力での搬出作業が増えるため、人件費が高くなります。
階段が狭い、廊下に曲がり角が多い、玄関が狭いなどの条件があると、大型家具や家電の搬出に時間がかかったり、解体作業が必要になったりすることもあります。また、駐車場から部屋までの距離が遠い場合も、運搬にかかる時間と労力が増えるため、費用が上がる要因となります。
作業期間と人員数
遺品整理にかかる作業期間と必要な人員数も、費用を決定する重要な要素です。通常、1Kから1DKの部屋であれば2名から3名のスタッフで半日から1日程度、3LDK以上の広い部屋や一戸建ての場合は4名から6名のスタッフで2日から3日程度かかることが一般的です。
急ぎの案件で短期間での作業を希望する場合は、通常より多くのスタッフを投入する必要があるため、人件費が増加します。また、土日祝日や早朝・夜間の作業を希望する場合も、割増料金が適用されることがあります。
特殊清掃の必要性
遺品整理と同時に特殊清掃が必要な場合は、費用が大幅に増加します。特殊清掃とは、孤独死や病死などで発見が遅れた場合に必要となる、専門的な清掃作業のことです。臭いの除去、体液や血液の清掃、害虫駆除などが含まれます。
特殊清掃が必要な場合、通常の遺品整理費用に加えて10万円から50万円程度の追加費用がかかることが多く、状況によってはそれ以上になることもあります。また、床材や壁紙の張り替え、消臭・除菌作業なども必要になる場合があり、これらも追加費用の対象となります。
実際の遺品整理費用の見積もり事例
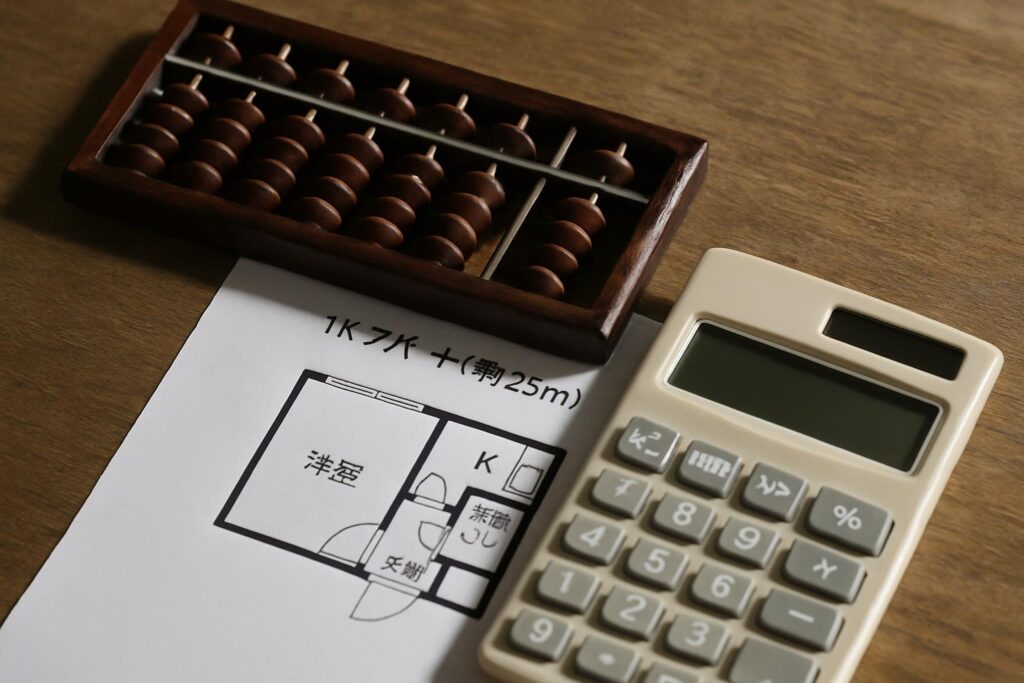
遺品整理の費用は、実際の現場の状況によって大きく変わります。ここでは、実際にあった遺品整理の見積もり事例をご紹介します。間取りや物量、作業内容による費用の違いを参考にしてください。
1Kアパートの遺品整理費用事例
東京都内の1Kアパート(約25㎡)での遺品整理の事例です。一人暮らしの高齢者の方が亡くなられ、ご遺族から依頼を受けました。
基本作業費用は8万円でした。内訳は、作業員2名での仕分け作業、不用品の搬出、室内清掃が含まれています。家具は冷蔵庫、洗濯機、テレビ、ベッド、タンスなど基本的な家電と家具のみでした。
追加費用として、エアコンの取り外しと処分に1万5000円、仏壇の供養と処分に2万円がかかりました。合計で11万5000円の費用となりました。作業は1日で完了し、立ち会いなしでの作業も可能でした。
2LDKマンションの遺品整理費用事例
大阪市内の2LDKマンション(約60㎡)での遺品整理の事例です。ご夫婦で住まれていた部屋で、物量は一般的な量でした。
基本作業費用は18万円でした。作業員3名で2日間かけて、リビング、寝室、和室の遺品を仕分けし、搬出作業を行いました。大型家具として、ダイニングテーブル、ソファ、食器棚、洋服タンス3棹、仏壇などがありました。
貴重品の捜索サービスを追加で依頼され、通帳や印鑑、貴金属などを探し出す作業に2万円かかりました。また、大量の書籍があったため、古本の買取業者を手配し、買取金額3万円を費用から差し引きました。最終的な支払い金額は17万円となりました。
一戸建て住宅の遺品整理費用事例
埼玉県の一戸建て住宅(4LDK、延床面積約120㎡)での遺品整理の事例です。長年住まれていたため、物量が多く、庭の物置にも多くの荷物がありました。
基本作業費用は35万円でした。作業員4名で3日間の作業となりました。1階のリビング、ダイニング、和室、2階の寝室3部屋、さらに物置と庭の不用品まですべて整理しました。
特に費用がかかったのは、ピアノの処分で3万円、庭木の伐採と処分で5万円でした。また、遺品の中から骨董品や着物が見つかり、専門の買取業者に査定してもらったところ、8万円の買取となりました。最終的な費用は35万円となりました。
高額になった遺品整理費用事例
神奈川県の2階建て一戸建て(5LDK)で、特殊な事情により高額になった事例です。ご高齢の方が一人で住まれていて、いわゆる「ごみ屋敷」状態になっていました。
基本的な遺品整理費用は50万円でしたが、床が見えないほどの物量があり、通常の3倍以上の時間がかかりました。作業員5名で5日間の作業となり、2トントラック8台分の不用品が出ました。
さらに、室内で亡くなられていたため、特殊清掃が必要となり、床材の張り替えと消臭・除菌作業に25万円かかりました。害虫駆除にも3万円必要でした。また、近隣への配慮から、早朝や深夜の作業は避け、防音シートを設置するなどの対策費用に5万円かかりました。
最終的な費用は83万円となりましたが、このような特殊なケースでは、事前の現地調査が特に重要であることがわかります。見積もり時に詳細な状況を確認し、追加費用の可能性についても説明を受けることが大切です。
遺品整理の費用を安くする5つのコツ

遺品整理の費用は決して安くありませんが、工夫次第で大幅に節約することができます。ここでは、実際に多くの方が実践して効果を実感している5つのコツをご紹介します。
事前に自分でできる整理を進める
遺品整理業者に依頼する前に、自分でできる範囲の整理を進めることで、作業量が減り費用を抑えることができます。まず、明らかなゴミや不要な紙類、古新聞などは自治体の収集日に合わせて処分しましょう。
衣類や日用品も、リサイクルショップへの持ち込みや、自治体の資源回収を利用することで、業者の処分費用を削減できます。ただし、無理をせず、重い物や大型家具は業者に任せることが大切です。
形見分けについても事前に親族間で話し合い、必要なものを引き取っておくことで、業者の仕分け作業時間を短縮できます。これにより、人件費の削減につながります。
買取可能な品物を分別しておく
遺品の中には、意外と価値のあるものが含まれていることがあります。貴金属、ブランド品、骨董品、切手、古銭などは、買取対象となる可能性が高いです。これらを事前に分別しておくことで、買取査定がスムーズに進みます。
家電製品も製造から5年以内のものであれば、買取可能な場合が多いです。また、家具も状態が良ければ買取対象となることがあります。買取金額は遺品整理費用から差し引かれるため、実質的な負担を軽減できます。
書籍やCD、DVDなども、まとめて買取業者に依頼すれば、処分費用がかからないだけでなく、買取金額が期待できる場合もあります。
複数の業者から見積もりを取る
遺品整理の費用は業者によって大きく異なります。最低でも3社以上から見積もりを取ることをおすすめします。見積もりを比較する際は、金額だけでなく、作業内容や追加料金の有無も確認することが重要です。
見積もりは必ず現地調査をしてもらい、詳細な内訳を書面でもらいましょう。電話やメールだけの概算見積もりでは、後から追加料金が発生するリスクがあります。
また、相見積もりを取っていることを業者に伝えることで、価格交渉の余地が生まれることもあります。ただし、極端に安い業者は、不法投棄のリスクや作業品質に問題がある可能性もあるため、注意が必要です。
繁忙期を避けて依頼する
遺品整理業界にも繁忙期と閑散期があります。3月から4月の引っ越しシーズンや、12月から1月の年末年始は依頼が集中し、料金が高くなる傾向があります。
可能であれば、6月から8月の夏場や、10月から11月の秋口など、比較的依頼が少ない時期を選ぶことで、費用を抑えることができます。また、平日の依頼は土日祝日よりも安くなることが多いです。
急ぎでない場合は、業者と相談して、スケジュールに余裕を持たせることで、割引を受けられる場合もあります。業者側も効率的にスケジュールを組めるため、お互いにメリットがあります。
地域密着型の業者を選ぶ
大手の遺品整理業者よりも、地域密着型の中小業者の方が、費用を抑えられることが多いです。地域密着型業者は、移動コストが少なく、地元の処分場との連携も取れているため、効率的に作業を進められます。
また、地域の評判を大切にしているため、丁寧な作業と適正価格でのサービス提供を心がけている業者が多いです。口コミや地域の評判を確認し、信頼できる業者を選びましょう。
地元の業者であれば、アフターサービスも受けやすく、万が一のトラブルにも迅速に対応してもらえるメリットもあります。遺品整理士の資格を持つスタッフがいる業者を選ぶことで、より安心して依頼できます。
遺品整理業者の選び方と費用の確認ポイント

遺品整理を依頼する際、適正な費用で質の高いサービスを受けるためには、業者選びが重要です。ここでは、信頼できる業者の見分け方と、費用面で注意すべきポイントを詳しく解説します。
信頼できる遺品整理業者の見分け方
まず、遺品整理士認定協会が認定する「遺品整理士」の資格を持つスタッフが在籍しているかを確認します。この資格は、遺品整理に関する専門知識と倫理観を持つ証明となります。
次に、一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているか、または許可業者と提携しているかを確認することが大切です。この許可がない業者は、適切な廃棄物処理ができない可能性があります。
料金体系が明確に提示されているかも重要なポイントです。ホームページや資料に、基本料金や追加料金の条件が詳しく記載されている業者は信頼性が高いといえます。電話での問い合わせ時に、概算でも料金の目安を教えてくれるかどうかも判断材料になります。
実績や口コミも確認しましょう。創業年数や年間の施工件数、実際の作業事例が公開されているかをチェックします。また、第三者の口コミサイトでの評価も参考になります。
損害賠償保険に加入しているかも重要です。作業中の事故や物品の破損に備えて、適切な保険に加入している業者を選ぶことで、万が一のトラブルにも対応できます。
見積書で確認すべき費用項目
見積書を受け取ったら、まず基本作業料金の内訳を確認します。人件費、車両費、処分費用などが含まれているか、それぞれの金額が明記されているかをチェックしてください。
作業範囲も明確に記載されているか確認が必要です。どの部屋のどこまでを整理するのか、庭や物置は含まれるのか、エアコンや照明器具の取り外しは含まれるのかなど、具体的な作業内容が記載されているかを見ます。
処分費用については、品目ごとの単価が示されているかを確認します。家電リサイクル法対象品目の処分費用、粗大ごみの処分費用、一般ごみの処分費用などが分けて記載されていると、後から追加料金が発生するリスクを減らせます。
オプション料金についても確認が必要です。階段での搬出作業、エレベーターなし物件での追加料金、特殊清掃が必要な場合の料金、仏壇や神棚の供養費用などが別途必要になる場合があります。
買取可能品がある場合の取り扱いも重要です。買取金額を作業費用から差し引いてくれるのか、別途精算になるのか、買取できない場合の処分費用はどうなるのかを確認しましょう。
契約前に確認すべき注意点
キャンセル料の規定は必ず確認してください。いつまでなら無料でキャンセルできるのか、キャンセル料が発生する場合はいくらなのかを把握しておくことが大切です。
作業日程の変更についても確認が必要です。天候や体調不良などで日程変更が必要になった場合、追加料金が発生するのか、何日前までなら変更可能なのかを聞いておきましょう。
支払い条件も重要なポイントです。作業前の前払いなのか、作業後の後払いなのか、分割払いは可能なのか、クレジットカードは使えるのかなど、支払い方法と時期を確認します。
追加料金が発生する条件も明確にしておく必要があります。見積もり時に確認できなかった物品が出てきた場合、予想以上に汚れがひどかった場合など、どのような状況で追加料金が発生するのかを事前に確認しておきます。
最後に、作業完了の基準を確認します。どの状態になったら作業完了とみなすのか、清掃はどの程度まで行うのか、立ち会い確認は必要なのかなど、作業終了時のルールを明確にしておくことで、トラブルを防げます。
遺品整理の費用に関するよくある質問

遺品整理の費用は誰が負担するのか
遺品整理の費用は、原則として相続人が負担することになります。民法では、相続人は被相続人の権利義務を承継すると定められており、遺品整理にかかる費用も相続財産から支払うことが一般的です。
相続人が複数いる場合は、法定相続分に応じて費用を分担することが基本となります。ただし、相続人同士で話し合い、異なる割合で負担することも可能です。遺産分割協議の中で、遺品整理費用の負担についても明確に決めておくことが大切です。
相続放棄をした場合は、遺品整理の費用を負担する義務はありません。しかし、相続放棄の手続きは相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で行う必要があります。この期限を過ぎると単純承認したものとみなされ、費用負担の義務が生じます。
賃貸物件の場合、連帯保証人も費用負担を求められることがあります。相続人がいない、または全員が相続放棄した場合、連帯保証人が原状回復のための遺品整理費用を負担するケースもあります。
支払い方法とタイミング
遺品整理業者への支払い方法は、現金払い、銀行振込、クレジットカード払いが一般的です。最近では、PayPayやLINE Payなどの電子決済に対応している業者も増えています。支払い方法は業者によって異なるため、事前に確認することをおすすめします。
支払いのタイミングは、作業完了後の一括払いが基本です。ただし、高額な場合は着手金として費用の一部を前払いし、残額を作業完了後に支払うケースもあります。着手金は総額の30~50%程度が相場となっています。
分割払いに対応している業者もありますが、すべての業者が対応しているわけではありません。分割払いを希望する場合は、見積もり時に相談し、支払い条件を明確にしておくことが重要です。分割回数や手数料の有無についても確認しましょう。
領収書は相続税の申告や遺産分割協議の際に必要となることがあるため、必ず受け取って保管しておきます。明細が記載された領収書を発行してもらうことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
費用が予算を超えた場合の対処法
見積もり金額が予算を超えてしまった場合、まず作業内容を見直すことから始めます。すべてを業者に任せるのではなく、自分たちでできる作業を増やすことで費用を抑えられます。例えば、貴重品の仕分けや小物の整理は家族で行い、大型家具の搬出や処分のみを業者に依頼する方法があります。
作業を段階的に進めることも有効な対処法です。まず必要最小限の部屋から整理を始め、予算に余裕ができたら次の部屋に進むという方法です。賃貸物件の場合は退去期限があるため難しいですが、持ち家であれば時間をかけて整理することが可能です。
買取可能な品物がある場合は、それらを先に買取業者に売却し、その売却代金を遺品整理費用に充てることもできます。ブランド品、貴金属、骨董品、家電製品などは意外な高値で売れることがあります。複数の買取業者に査定を依頼し、最も高い価格を提示した業者に売却しましょう。
自治体によっては、高齢者世帯や生活困窮世帯向けの支援制度を設けている場合があります。社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度を利用できることもあるため、市区町村の福祉窓口に相談してみることをおすすめします。また、故人が生活保護を受給していた場合は、葬祭扶助として遺品整理費用の一部が支給される可能性もあります。
まとめ

遺品整理の費用は、間取りの広さや物量、建物の条件などによって大きく変動します。1Kで3万円~8万円、2LDKで8万円~25万円、一戸建てで15万円~50万円が相場となっています。費用を抑えるためには、事前に自分でできる整理を進め、買取可能な品物を分別し、複数の業者から見積もりを取ることが重要です。
また、繁忙期を避けて依頼することで、より良い条件で契約できる可能性があります。信頼できる業者を選び、見積書の内容をしっかり確認することで、適正な費用で遺品整理を進めることができます。